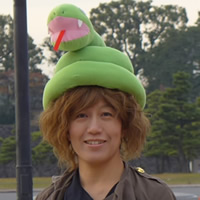和郷アグリカレッジ第一期に参加~半農半Xライフを目指して!<前編>
突然だけど、先月9月から「和郷アグリカレッジ」第一期に参加し、新規就農や地方移住、自然農法などに関心がある人達と一緒に研修を受けている。
過去一度も農業に関わったことはないが、テレビや本で「半農半X」というライフスタイルを実践する人たちの存在を知り、「将来そんな生活もいいなあ」と漠然と考えていたところ、SNS広告に募集告知が流れてきた。
親介護の関係でここ数年は都市部と実家がある千葉県香取市で二拠点生活をしており、昨年36年ぶりにUターン。母他界後は実家片づけをしながら庭や隣接する小さな畑で野菜を育て始めていた。介護が一段落したらまた都市部に戻ってIT関連の仕事を再開する予定だったが
「このまま香取で在宅仕事をしつつ、副業で小規模な畑をやるのもありかも」
なんて思い始めていたところだったので速攻申込み。その日のうちにZoom面談して研修生となった。
ちょうどカリキュラムの半分が終わったところなので、どんな内容なのかざっくり紹介したい。
INDEX
1.和郷アグリカレッジとは
2.全国から研修生が集っての「農業基本講座」
3.実地研修は3泊4日で生産者さんの話を聞き農作業体験
4.前半カリキュラムを終えて
和郷アグリカレッジとは
公式サイトがかなり作り込まれているので、私がここで半端に語るよりそちらを見てもらったほうが確実で早いと思う。
・生産・加工流通の他、農園リゾートの運営でも成功を収める農事法人・和郷が運営
・今回が第一期で、農林水産省の補助金により25万円の参加費は全額無料
・WEB面接を経て合格した研修生が約半年かけて就農に必要な知識・考え方などを学ぶ
・宿泊研修が全部で4回あり、初回だけ全地区の参加者が香取に集結して合同研修
・実地研修は秋田から鹿児島まで各地区ごとに日程や内容が異なる
・実地研修では、生産者を訪れ、話を聞いたり実際に作業を体験したりする
・農法を学ぶだけではなく、就農に必要な広範囲にわたる知識や情報、考え方を身に付けることができる
私は昨年から和郷の本社がある千葉県香取市にUターン居住しているので、香取市のチームに参加。こんな近場在住者は私くらいで、大半は東京・神奈川の都市部で暮らしている人達。さらには宮城県石巻市に移住した人や、秋田・宮崎から新幹線や飛行機でやってきている人もいた(補助事業で1回あたり往復5万円を上限に交通費も助成される)。
「作る作物によって農法も全然違うのに何を学ぶの?」
と疑問に思う方もいると思うが、実際には「農作物の作り方」を教わるのではなく、「新規就農に必要となる知識や心構え、考え方」などを教えてもらい、また様々なタイプの生産者さんから直接体験談や戦略などを聞くことで、研修生ひとりひとりが「自分はこんなスタイルで農業に取り組んでいきたい」というプランを具体化していくことが目的になっている感じだ。
詳細は後述するが、収入推移や反収(一反あたりの収量)、流通・小売りとの仕切りパーセンテージなど生々しい数字もポンポン飛び出し、どんな工夫改善によりどう効率アップ・収入アップになったかなど実績に基づく現場ノウハウの話もいっぱい。
自分のような知識ゼロの人はもちろん、就農を視野に既に情報収集を始めていた人達にとっても非常に新鮮で刺激的で、そして参考になる話がたくさん聞ける。
全国から研修生が集っての「農業基本講座」
初回だけZoomでカリキュラム説明や参加メンバーの自己紹介を行い、いよいよ研修本番の開始。
実地研修は各地域で行われるが、この「農業基本講座」だけは全研修生が千葉県香取市に集結する。人数が多いので二回に分けて行われ、私達の時には30名ちょっとだった。
研修内容&講師は公式サイトに書かれているとおり。
初日は完全座学で、和郷代表の木内氏、そしてトマトを栽培する佐藤農園の代表で和郷園の理事でもある佐藤氏、そしてこの和郷アグリカレッジの責任者である高橋氏の講義。
これが、どれも本当によかった!
木内氏の講演は、農業者大学校を出た後、実家に戻り家業である農業を始めた頃からの実体験に基づく話。眠くなるどころか「ワクワクする」「実話に基づくドラマとか作ったら大ヒットしそう!」など夜の懇親会でも大盛り上がりするほど、非常にリアルでエキサイティングで、農業という分野が秘める可能性を感じさせてくれる内容だった。
木内氏は、2009年6月にNHKプロフェッショナルにも登場している。
●プロフェッショナル仕事の流儀「誇りと夢は、自らつかめ 農業経営者 木内博一」
木内たちの農家グループは、平均年齢30代前半の若い農家の集団だ。それでも、主要メンバーの年間の売り上げは全国平均の2倍以上、なかには1億円を超えるものもいる。その華々しい実績を可能としたのは、木内たち農家が立ち上げた会社だ。市場を通さない野菜の出荷に加え、さまざまな事業に取り組み、その利益を元手にグループの農家の経営を安定させることに成功した。 新規事業を立ち上げる際に木内たちの考え方の出発点となっているのが、「"常識"を疑う」こと。従来の農家が"常識"としてきたことを見直し、本当にそれは正しいのかと疑い、もっと良い手立てがないかと模索する中から、木内たちはビジネスの種を見つけ出してきた。
こちらにも同様の話などが掲載されている。
●ちば起業家応援事業 INNOVATIVE HIVE「Model01 農事組合法人和郷園 代表理事 木内 博一」
佐藤氏の講演も、メモをとりまくった。
新規就農を目指す人達のサポートにも熱心に取り組む佐藤氏は、この講演のために何人もの新規就農者のところにインタビューに行き、就農の経緯や最初に何から始めたか、失敗したこと、転機、初期の畑の広さや初年度の売上など数字もふんだんに交えながら、ケーススタディをこれでもかというほどに披露してくれた。
「農業は儲からない」
なんてことはないという事実に、勇気づけられた研修生はきっと多かったと思うし、何を栽培するかということを考えるうえでもとても勉強になった。
高橋氏は、日本農業経営大学校イノベーター養成アカデミー客員教授でもあり、初回のWEB研修の時に続き、農業を始めるにあたってどんな情報リソースを活用できるのかといった話や様々なデータについて解説をしてくれ、これも本当に勉強になった。消化しきれていない部分もあるので、いただいた資料を後でもう一度じっくり読み直したい。
宿泊は、和郷グループが運営する「農園リゾートTHE FARM」の一画に最近できたばかりのコテージ「ハビタ」。ちなみにTHE FARMはプレスツアーや自腹で何度か泊りにきており、運営サイト「東京&関東グランピング情報館」にも訪問レポートを書いている。
●グランピング初体験ならここ!関東屈指の人気を誇る農園リゾート「THE FARM(ザ ファーム)」<前編>
●グランピング初体験ならここがおススメ!関東屈指の人気を誇る農園リゾート「THE FARM」<後編>
●人気グランピング「THE FARM」のサウナがいま熱い!
「THE FARM」のフランチャイズ1号のマザー牧場グランピングも体験した。
●【見学】開放感あふれる風景にこだわり施設~マザー牧場グランピング
●マザー牧場の新グランピング施設「Green Base」(前編)巨大ドームテント初体験!
●マザー牧場の新グランピング施設「Green Base」(後編)ディナーにアルパカとの記念写真も
香取市にUターンしてからは、THE FARM内の温泉施設「かりんの湯」がお気に入りで、回数券を買って通っているほどだ。
2日目は、そんな農園リゾート「THE FARM」を高橋氏の案内で視察しながら、オープンに至った経緯や試行錯誤をしていた初期のこと、農水省が推進する「都市農村交流」とは何なのかといった話など。
グランピングも、国内で大ブームが起きるより前から始めていて、行政や海外からの視察も多く受け入れている。コンサルなどはいれず、スタッフ手作りで細かい改良も重ねながら現在の形に至っている話などが本当に興味深かった。
利用者が求めているものは何なのか━━そこを徹底追及している姿勢が印象的だ。
ちなみにランチはTHE FARMカフェで、マッシュルームパスタを食べた。芳源マッシュルームも見学に訪れたことがあり、菅佐原社長ともFacebookで交流させてもらっているが、こちらも香取を代表する産品のひとつ。
●マッシュルームの一大産地・千葉県香取市「芳源マッシュルーム」米野井プラント見学
午後やマイクロバス2台に分乗して視察へ。
和郷ファームには大きなハウスが並び、中には試験栽培する実験棟も。
市場に求められているものが何かを追求しながら作付けしており、水耕栽培のことや苗のこと、肥料や農薬のこと、ハウスの作りや管理、注意点など教えてもらい、研修生からもたくさんの質問が寄せられた。
和郷では生産だけでなく、野菜のカット加工や冷凍なども行っており、冷凍工場「さあや'Sキッチン」も視察した。生産してそのまま出荷するだけでなく、加工・冷凍も行える施設を作ることでどのくらい売上が変わるのか、規格外の野菜なども加工すれば無駄にすることなくしっかり売上につなげられる。生産と出荷のバランスをとる重要な役割を果たしているといった話など。
和郷は生協との取引で一気に規模拡大しており、その最初のいきさつなどは前日の木内氏の講演でも聞いていたが、カットごぼうだけでなく、さつまいもスティックの話なども聞いて、「消費者・流通ニーズにこたえ、付加価値を高めるための不断の創意工夫」が和郷の強みなのだなとあらためて実感した。
ちなみに北総エリアはこの時、さつまいも収穫・出荷ピークの直前。敷地内には収穫用のケースが山と積み上げられていた。
和郷の本社敷地内にあるカット工場。
スーパーの総菜コーナーで調理する野菜をカットして出荷したりもしているが、その際ナスに入れる切込みをこちらの店用は何本、別の店用には何本といった、細かすぎるほどのオーダーにも応じて実現しているとのこと。
そこまでやるのか・・・と一同絶句した瞬間だ。
3日目には、この研修で学んだことや気付き、残る疑問や抱えている不安などを話し合う場が設けられた。
3日間同じコテージで過ごした4人がチームを作り、話し合い、模造紙にまとめ、発表する。立場・興味関心の違いで、同じ研修を受けていても誰のどんな話や施設見学が刺さったかは人によって異なる。
この時のディスカッションでもまた、新たな発見があった。
他の参加メンバーとの交流も、この研修の魅力のひとつだと思う。
初日夜はBBQ場で懇親会。
年齢も職業も本当に幅広く、住んでいる場所も北海道から鹿児島まで実に様々。
なぜ農業に興味を持ったのか、何を作りたいと思っているのか、講義や視察時の話を聞いてどう感じたか、日本の農業と食の安全など、話は止まることなく盛り上がった。
2日目の夜には、コテージのテラスに集まって飲みながら再び大宴会。熱い思いを抱いている人も多く、こんな人達と知合えたというだけでも、今回参加して本当によかったなと。
実地研修は3泊4日で生産者さんの話を聞き農作業体験
そして遂に実地研修の第一回が、昨日までの3泊4日で行われた。私は近かったので通いにしたが、他の研修生は全員ルートイン佐原に宿泊し、その宿泊料も今回は無料となっている(参加費25万円に宿泊料も含まれているのだろう)。
初日はスケジュール説明の後、THE FARMが観光農園として今冬から始めるいちご狩り用のハウスの見学。夜のいちご狩りができるようになるということで、ここ最近よく広告を見かけるようになった。
引率の高橋氏から、いちごの種類やパテントのこと、観光農園で多く採用されている高設ベンチ、そして観光農園の採算やコストの話などいろいろ伺った。
2日目は2チームにわかれ、我々はミニ白菜・ベビー白菜を育てる旭市の農家の方の畑へ。
実際にベビー白菜「娃々菜」の定植作業も体験させてもらった。
家庭菜園ではせいぜい1種類の苗を10本も植えれば多いほうだったりするので、延々と続く畝にひたすらポット苗を差し込んでいく作業は初めてだ。自分達以外に、タイ人の研修生グループも定植作業を行っていたが、スピードが全然違った。
「親指一本で穴をあけてそのままこうやって押し込めばいい」など親切に教えてもらったりもして、結構楽しい作業だった。
定植した苗はぐったり横たわってしまっていたが、雨がふれば元気になり、あっという間に育つそうで、定植から1週間後、さらに10日後の畑もその後見学させてもらった。
こうなって・・・
さらにこうなる。
この後中心部分が結球(葉が何重にも重なって丸まること)を始め、最終的には300~500g程度になって出荷される。
今回研修生を受け入れてくれた加瀬さんは異なる職種から農業へと入ってきた方。
初期の頃の体験話や、ミニ白菜やそれより更に小さなベビー白菜「娃々菜」が消費者に人気な理由、それぞれの採算の話、土作りのこと、ハウス栽培や露地栽培のこと、旭市特有の土や水のことなど、本当に多岐にわたるお話を伺うことができた。
今回の和郷アグリカレッジとは関係ないが、加瀬さんがルッコラについて語っている動画がある。
3日目はさつまいもなどを栽培する法人として農場を運営する有限会社さかき。
実はここ、和郷代表の木内氏の実家で、社長を務めている弟の木内氏が今回研修生に話をしてくれた。
建築の仕事をしていた20代の頃、お兄さんから一緒にやろうと誘われて戻ってきたこと。当時は「長男だって跡をつがないご時世に、男兄弟ふたりで実家の農業をやるなんて」と実の両親を含め周囲から大反対だったのだとか。
そんな話から、さつまいも栽培の話、先進的な施設園芸栽培で高い成果をあげているオランダの話、土作りのこと育苗のこと害虫の話など、2時間近くみっちりお話をしてくださった。
さつまいも収穫の掘り上げに使われる「ポテカルゴ」。
本当はサツマイモ掘りも体験できる予定だったが、残念ながら朝方まで大雨だったのでできず。
替わりにツル切りを体験させてもらった。
複数のさつまいもがツルについた状態になっているので、それをツルちょっとだけ残してハサミでカットしていくという作業。
木内兄弟のお父さまも作業をされており、ごぼうをカットして出荷して大成功した話などを聞かせてくれた。
作業後に食べた茹でたて大粒落花生の美味しかったこと。お土産にもたっぷりもらった。
その後キュアリングが行われている倉庫に見学に行き、最後に選別作業が行われている倉庫を見学に。
ここではタイ人研修生に加え、北海道から派遣されてきたというインドネシア人達が黙々と、サイズや形、へこみや皮のキズなどの状況に応じて分類しカゴに入れていく作業をしていた。
空前の人手不足で、外国人研修生の助けがなければ到底まわらないとのこと。夜遅い時間まで作業が続くそう。
案内してくれた方は、新規就農をするのであれば、こうした人手確保、人件費というものが大きな課題にもなってくるという話をしてくれた。
実地研修4日間のうち、実際に生産者を訪ねて話を聞いたり作業体験をするのは中2日間で、最終日は和郷が運営に関わっている橘ふれあい公園でオリエンテーリングを行い、最後佐原駅で解散となった。
次は12月だ。
4日間楽しく過ごした研修生仲間ともしばしのお別れとなる。
前半カリキュラムを終えて
帰途、ちょうど収穫祭イベントをやっていた「道の駅さわら」に立ち寄り、売られていた全種類のさつまいもを買ってみた。こんな買い方をしたのは初めてだ。
今回さつまいもの品種やブランドの話を詳しく教えてもらったので、食べ比べてみようかなと思って。
数が多いのは、8月の入院時にお見舞いをもらった人達に、さつまいもの詰め合わせを送ることにしたからだ。道の駅だと1本単位でも買えるので、それを詰め合わせたらもらったほうもきっとびっくりするはず。
産地の道の駅や産直販売店以外でこれだけの種類が買えることはあまりないし、あっても1袋4~5本入っていたら複数種類を買うことはできない。
「食べ比べできるさつまいもセット」なんて売り方もありかもしれない。
ホームセンターには「千葉県産さつまいも」と書かれた5キロ用段ボールが1枚99円で売られていたので、それも送る人数分買ってみた。
次のアクションはこれだ。
実家の家庭菜園の畑・・・だった跡地。
この春、手押しの耕運機をレンタルして耕し、畝を5本くらい作って野菜の苗や種イモを植え付けたものの、5月に後縦靭帯骨化症という病気が発覚して畑作業が中断となり、2週間の入院を経て戻ってきたら、畝ごと雑草に埋もれてしまった。
まずはここの草を刈り、もう一度耕運機を借りて畝をたて、10月中に何を作るか決めて種まき・苗定植を行う。そしてトンネルにして、冬の間中の自分が食べる野菜をここから調達できるようにしたい。
この畑(だった場所)が230平米あり、それとは別に家がある敷地にも100平米くらい空いている場所があるので、そこでも何か作ることができる。今までは、ほうれん草と小松菜、あとキュウリやトマト、ナス、いんげんやスナップエンドウ、じゃがいもといった家庭菜園定番のものしか作ってこなかったけど、今回お話を伺ってミニ白菜も作ってみたくなったし、ルッコラやパクチーも少しあったら毎朝のサラダにトッピングできて楽しいかもなと。
一冊ノートを作って記録しながら、いろいろな作物作りに挑戦してみたい。
そしていずれ、もっと本格的にやる自信がついたら、半農半X生活のスタートだ。
今回、この和郷アグリカレッジに参加したことで、新しい可能性が見えてきた気がする。
12月と1月にも実地研修を受けるので、終わったらまたここで報告したい。
そして家庭菜園の様子も、随時、当ブログやインスタグラムで発表したいと思う。































 X(旧Twitter)アカウントはこちら
X(旧Twitter)アカウントはこちら