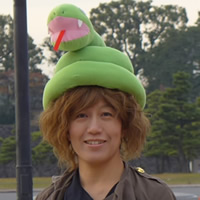"収穫"体験を手軽に楽しめる「活き野菜プロジェクト」始動!

2024年9月に参加した農業研修「和郷アグリカレッジ」の全カリキュラムが終了しました(前編レポート)。
本当に楽しかったし、たくさん学べました!
後編レポートは後日作成しますが、今回は私がチャレンジしたい「活き野菜プロジェクト」についてです。
INDEX
1.活き野菜プロジェクトって?
2.まずはベビーリーフからスタート
3.販売はマルシェやイベントで
4.インテリアとしても楽しめる提案を
5.3月の販売に向けて本格始動!
6.このプロジェクトで実現したいこと
活き野菜プロジェクトって?
収穫前の「活きている野菜」をマルシェやイベントなどで販売するというものです。
写真をお見せしたほうが早いと思うので・・・
これです ↓
私は毎朝、家庭菜園でベビーリーフやサラダ小松菜などを収穫して、そこに蒸し鶏ささ身や温泉卵をトッピングして食べています。
以前はレタスやベビーリーフを毎週スーパーで買っていましたが、家庭菜園を始めてから、サラダ素材の野菜を買いに行く手間も減り、冷蔵庫でうっかりしおらせてしまうこともなくなりました。野菜高騰でも安心ですし、なにより自分で作った新鮮な葉野菜を毎日食べられる生活は幸せです。
でもこれも、田舎にUターンして畑があるからできること。
都市部で生活している時もベランダ菜園や室内での水耕栽培に挑戦したものの、うっかり何度も枯らしてしまいました。
・ホームセンターが近くになく土や鉢を用意するのが大変
・気付くと水やりを忘れちゃう
・収穫までに結構時間がかかってじれったい
・栽培しなくなった後の植木鉢の処分に困る
・長い間待った割にはそんなに食べられない
「やりたいのは栽培じゃなくて収穫!」という人もいると思います。
そこでこう考えました。
すぐ収穫できるベビーリーフやハーブを「活き野菜」として販売したらどうだろう。
それなら買った人がすぐ収穫して食べられるし、料理の添え物などにちょっとずつ使うことだってできる。
持ち運びも楽で処分も簡単な不織布ポットを植木鉢替わりに栽培すれば、環境にもやさしい。
早速、試作してみることにしました。
まずはベビーリーフからスタート
最初はベビーリーフです。
自分も毎日食べていますし、育成が早いので検証もしやすく、何より見た目がかわいい♪
ホームセンターで野菜の培養土を買ってきて、タネを蒔いたのが12月。
冬でも室内ならすぐ芽吹いてくれます。
双葉がにょきにょき顔を出して本当にキュート♪
余っていた角材を切って、専用の育成棚も作りました。
10度を切ると発芽率も下がってしまうので、簡単なヒーターパネルも設置して、夜間だけつけることに。
第一弾は、欲しいといってくれた友人などに配りました。
家で育て始めたら、愛着がわいて食べられなくなってしまったなんて声も。
いつもの肉料理にちょっと添えるだけで、食卓がグレードアップすると言ってくれた人もいます。
アボカドや海老をトッピングして食べてくれた人も。
くせがなくてよかった、もっと大容量のものが欲しいというリクエストももらいました。
ベビーリーフは、何種類かの異なる葉野菜の若い葉をミックスしたもの。市販のタネはメーカーによって含まれる葉野菜の種類が異なり、見た目も変わります。
そして種類が違えば、味わいや食感も変わります。
サカタ公式サイトでは、ベビーリーフに適した葉野菜のタネが種類別に購入できるので、一種類ずつのポットも作って、好きな葉を組み合わせて買ってもらうのも面白いかもと考えています。その日の気分に合わせ、自分だけのオリジナルベビーリーフを作るなんて楽しみ方もできますし。
販売はマルシェやイベントで
課題は「興味を持ってくれそうな人のもとにどう届けるか」です。
収穫後のベビーリーフなら、パッキングして道の駅などで販売することもできますが、「収穫前」の状態はかさばりますし、慎重な運搬が必要なので流通には乗せにくいです。
そこで、自分の車に積んで運び、マルシェやイベントで販売することにしました。
対面なら食べ方や育て方も説明できますし、もし自分でも育ててみたいという人がいたら、未使用の不織布ポットや土をお分けすることもできます。
ちなみにこれは、大井競馬場で頻繁に開催されているフリーマーケット。
昨年初めて出店して、実家にあったこけしや木彫りの置物を外国人観光客の方などに買ってもらいました。
人気も高い、東京・有楽町の交通会館マルシェ。
こだわり野菜を販売している人も多く、このミニ多肉植物のお店が本当に素敵でした。
インテリアとしても楽しめる提案を
すぐ収穫して食べてしまうのもよし、ちょっとずつ使いながら、インテリア・観葉植物として楽しむこともできます。
100円ショップで売っている箱やカゴなどにビニールを敷いて並べてもいいでしょう。無印良品の天然素材のケースやかごと合わせてもよさそうです。そんな陳列方法も一緒に提案してみたいところ。

あと先月から竹細工講座に通い始めたので(関連記事)、いつか活き野菜を引き立たせてくれる専用竹カゴも作りたいです。
インスタでは、活き野菜の活用方法や楽しみ方をシェアしていく予定です。
ハッシュタグは「#活き野菜」「#活き野菜がある生活」。買ってくれた方や興味持ってくれそうな方ともつながっていけたらうれしいですね。
夢だけは拡がります♪
3月の販売に向けて本格始動!
今週末、3月のマルシェ初出店を目指し準備を開始しました。
まずは種まきです。
ホームセンターで野菜培養土を買ってきて不織布ポットに入れ、4種類のタネを蒔きました。
育てるのは日当たり抜群の我が家のサンルーム。
家の中なので虫もおらず、もちろん農薬は一切不要です。
食品衛生責任者のeラーニングも受講開始しました。
生野菜サラダとして食べてもらう前提なので、育成中はもちろんのこと、運搬・販売時にも衛生面に十分留意したいと思います。
このプロジェクトで実現したいこと
畑でサラダ用の野菜を育てるようになって、「自分で栽培して自分で収穫して食べる」魅力に目覚めました。そして農業研修では情熱に満ちた生産者の方々からお話を伺い、
「野菜作りをライフワークにしたい」
という思いを強めました。
この「活き野菜プロジェクト」で実現したいのは、家庭菜園のハードルをぐんと下げ、手軽に「野菜収穫を楽しめる」「美味しい緑がある」生活の実現です。
家庭菜園を始めようと思ったら、ホームセンターに行って植木鉢やプランタと土、肥料、タネや苗などを買ってこなくてはいけませんが、都市部で車もないとホームセンターに行くこと自体が難しかったりします。そしてタネ・苗から育てるのは時間もかかるし手間もかかります。
活き野菜なら育てる過程なしですぐ収穫できるし、「ちょっとだけ使いたい」ニーズや一人暮らしの人にもぴったりで、子供の食育にもなります。
そして全部食べ終わったら、新しい「活き野菜」を調達すればいいんです。「また枯らしちゃった・・・」と自責する必要もありません。その前に食べちゃえばいいだけです。
きっと、ベランダ菜園や水耕栽培に挑戦してみたくなる人も現れるでしょう。
野菜を育てるのは楽しいですし、癒しにもなります。多くの人が自宅にミニ菜園を作ったら、食料自給率がほんのわずかあがるかもしれません。
「野菜収穫をもっと手軽に楽しめる仕組みを作る」
これを目指して、活き野菜プロジェクトを推進していきます!

























 X(旧Twitter)アカウントはこちら
X(旧Twitter)アカウントはこちら