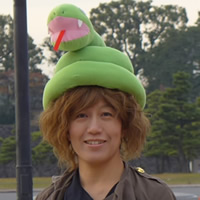築44年の実家和室をセルフリノベーションしてみた(3)
2024年7月に始めた人生初のセルフリノベ。
7月の壁・床剥がし&床下処置、9月中旬~10月の床下&壁作りと進み、遂に11月から、壁施工の最終工程、壁紙貼りの行程に入りました。
その前に、下地となる石膏ボードの表面をなるべく平らにする作業が必要です。石膏ボードのつなぎ目や、固定に使ったビスの頭が、壁紙を貼った時に表に響いてしまわないようにするためです。
省略する人のほうが多いと思いますが、ファイバーテープを使いました。これを石膏ボードのつなぎめに貼り付けることで、石膏ボードの端を安定させ、パテのノリをよくなるのだとか。
あと塗装もこの段階でやりました。
天袋は、扉を取り外して飾り棚として使うことにしたのですが、縁の木材が色あせていて、サンダーで磨いても残る劣化が気になったので・・・
アサヒペンの水性塗料で塗ることにしました。ウォールナッツという濃い目の色です。
初めてにしては上出来です(自画自賛)。
ちょっと濃すぎかな?と思ったけど、脳内シミュレーションでは、完成したらこの枠がいいアクセントになるはず。
石膏ボードのつなぎ目や、ビスの上に塗るパテは、開封すればすぐに使えるセメダインの製品を購入してみました。1キロも入っているからこれで足りるだろうと思ったら、なんと部屋の半分ほどで終わってしまう羽目に。
白いのがパテを塗った跡です。点線になっているところは、ビスをうった場所。ビスは石膏ボードにわずかにめり込ませていますが、そのままだと壁紙ごしにわずかな凹みが響いてしまうので、パテを塗ってまっ平らにする必要があるのです。
ケチりながらパテ塗り作業をするとなかなか平らにならず、時間もパテも逆に浪費してしまうということで、次は粉のパテを買って、自分で練って使いました。これだとたっぷり塗って、さっとへらで平らにできるので、美しく仕上がります。
最初の頃にやった場所の、美しくないことったら(涙。
まあいいんです。紙やすりで平らにできるし、壁紙を厚手のものにすれば、それほど響かないはずなので。
パテが乾いたら、紙やすりで滑らかな平らにして完了です。電動サンダーだと削りすぎちゃうかもと思ったので、手作業用の台座を買いました。
壁紙は、事前に「壁紙屋本舗」という大手オンラインショップからサンプルを有料取り寄せして決めていました。
11月29日。
ついに最終ステージ・壁紙貼りに辿り着きました。
簡単に使える「生のり付壁紙」なので、届いてから2~3週間以内に貼らないといけませんし、一度貼り始めたら重ね合わせながらやる必要がある関係で、短期決戦です。
壁紙貼りの作業だけは、数年前に2階の自室でやっていたので、多少は経験値があります。
右利きの人は、右端から貼り始めます。たとえその場所が、押入れの棚の突起ありエアコンありで一番難しい場所だったとしても。出窓のところはカットでちょっと失敗してしまいましたが、まあ素人だし自分の家なのだから細かいところは気にしない。あばたもえくぼって言いますし。
ひとつ後悔したのは、「柄合わせが必要な難しい壁紙を選んでしまった」こと。模様がずれないよう重ね合わせるところが結構難しいんです。
え、無地なのでは?と思われた方もいると思いますが、近付いてよく見ると・・・
実はレンガ柄。模様が微妙過ぎて、柄合わせが余計に大変でした。
思いの他苦戦して、半日でやっと一面。
夜中の24時直前まで作業し続けて、やっと二面。
翌日、作業を再開しようとして大きなミスに気付きました。
天井の端のあまりをカッターで切る作業をしようとしたところ、ノリが乾いて天井に張り付き、それを剥がそうとすると天井の古い合板の木目模様が剥がれてしまうのです。ドライヤーで温め、壁紙の表面の層だけを剥がし、その下の薄い紙を霧吹きで湿らせてゆっくり剥がすという作業でなんとかなりましたが、1時間半以上無駄にしました。
さらに、天袋の裏に青緑ぽい色の壁紙を貼り、一番奥の北側の壁には濃い木目模様の壁紙を貼りました。
この作業が終わったのが、日付を越えた12月1日の深夜2時半頃のこと。「11月中に壁紙貼りまで終わらせたい」というデッドラインはちょっと超えてしまいましたが、なんとか終わりました。
そして下の写真、12月1日の朝に撮ったものです。
いえーい (^^)/
残るは南側の押入れです。
ここ、床下収納を検討していた関係もあり、床も作らず状態でした。
でも結局、そのプランは見送り、12mmの合板で塞いじゃいました。
余計な収納を作るより、モノを減らすことに注力すべきだなと思い直して。
奥の壁は石膏ボードを窓とその周囲の木の形にぴたりくりぬいてハメました。これ1か月前だったら苦戦しまくって最後は石膏ボードを分割したと思うのですが、一発成功。
短い期間ではありますが、スキルはじわじわあがっています。
広いほうの押入れの天井にはベニヤ板を取り付けました。
一人作業だと、こういう「押さえながらビスで固定」という作業が大変だったりするのですが、それも工夫次第でなんとかなります。今回は丸のこなどでカットする際の作業台用に買ったAmazonベーシックの台を使いました。
押入れの床&内側の壁も完成!
この後、広いほうの押入れの上段床にはクッションフロアを敷きました。床部分は部屋の床と同じフロアタイルを。
右側の細い押入れは、入口にカーテンをつけるのと、衣装ケースや棚などを設置するので壁と床はベニヤのまま。
コンセントはもともと押入れ下の右側の壁だけだったのを、左にもう1か所増やしました。
同時進行で進めていたのが、障子やふすま、扉など建具のリメイク。
元々和室だったので、出窓の窓には障子が取り付けられていました。それをばりばり破いて・・・
古くなった障子枠を塗装。
最初に買った200ccの缶は途中で終わり、追加で700ccの大きな缶を買いに行きました。
人生初だった障子張り替え作業もうまくいって喜んでいたものの・・・
ガーン (+_+)
出窓の天井部分にベニヤ板を一枚貼っていたため、高さが微妙に変わってしまいはめ込むことができなくなってしまいました。
出窓天井をやり直すか、障子脇の下部を際カンナかジグソーなどで削るしかないのですが、どちらも持っていません。一旦保留としました。
そして扉。
吊るし引き戸にしようかと思って、その取り付け具も買っていたのですが、今回は元のままレールにはめ込む扉にすることに。
古く黄ばんだふすま紙を剥がしました。
こちらは天袋のふすまです。
44年前の施工の際の鉛筆メモ書きが残されています。
浪川さん・・・親からその名前を聞いた記憶があるので、家を建ててくれた工務店か人の名前かも。
メインで使っている白レンガ柄の壁紙を貼って・・・
取付完了!
Amazonで買ったアコーディオンカーテンもぴったりです。
これは部屋入口廊下側に取り付けられていた照明スイッチ。
セルフリノベ中の部屋に加え、トイレと階段の照明スイッチも一緒です。
今回はこれを、パナソニックのコスモワイドという大き目スイッチにしました。
コスモワイドは新しい規格ですが、それ以外のパーツなどは44年前も今も一緒です。規格がずっと変わっていないってすごいことですよね。
ちなみに、高さは変えました。
今は車椅子の人や子供でも届きやすいよう、スイッチの設置推奨位置は昔より下がっているそうです。これで確か下から115cmくらい(スイッチの上下中央が)。
床もサンプルを取り寄せました。
・フローリング材
・フロアタイル
・クッションフロア
の選択肢がある中、当初は安くて敷くのも簡単なクッションフロアにする予定だったのですが、気が変わってフロアタイルにしました。
フロアタイルの特徴は、2mm程度と薄いので取扱いが楽で、カッターで切れること。最終的にはボンドを全面に塗って貼り付ける必要があるのですが、並べただけでも特に問題はないので、家具配置などを決めるまでは貼らずに使うことにしました。
並べ終わりました。
壁と床の境目には、フロアタイルの隙間などもできてしまうので、「巾木」と呼ばれる木もしくはアクリル製のものを取り付けていきます。
近くのホームセンターには置いておらず、できれば床や壁にしっくり馴染む色のものにしたいので、ここは焦らず、実物を見て買えるお店を探そうと思います。
この段階でセルフリノベはほぼ完成しているのですが、この後PCデスクや折りたたみベッド、ラグ、間接照明など運び入れる予定なので、全部終わったらまた最終記事をアップしたいと思います。
> 続く



































 X(旧Twitter)アカウントはこちら
X(旧Twitter)アカウントはこちら