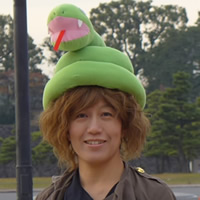築44年の実家和室をセルフリノベーションしてみた(2)
この記事の続きで、とあるコミュニティ内に書いた日記がベースです。
2024年7月に突如スタートした実家和室セルフリノベ。
壁&床をバールで剥がし、地面の土も見えている状態で床下の白アリ防止や調湿処理を行い、傷んでいた木材(根太)の交換などを行って床下地の荒板を並べて乾燥させるところまで7月内に辿り着きました。
8月から9月中旬までは休止。その後作業再開して床板を張り、新しい壁を作る作業を進行。
そして先に結論━━。
築44年目の砂壁和室が・・・
!(^^)! トランスフォーム!
これは去年12月1日朝の写真です。
なんとか11月中に壁紙まで貼り終えたいと、夜中2時過ぎまで作業した翌日、朝日が差し込む部屋を見て、ひとりニマニマしていました。久々の達成感です。
そんな50代半ば・経験値ゼロ女性が独力で取組んだ初めてのセルフリノベ過程のうち、床下断熱~壁作り作業までを今回ご紹介します。
まずこれが前回の最後、7月31日時点です。
床下地になる荒板を並べ、入院期間で乾燥させることにしました。安い板なので、時間とともに反りが出てしまうものもあるだろうと思ったので。両面には白あり防止剤の「シロアリミケブロック」をたっぷり噴霧してあります。
その後、人生初の3週間入院。
詳細はこちらに書きましたが、後縦靭帯骨化症という指定難病になり、頚椎の後ろを切り開いて、間の空間を広げてボルトで固定するという手術。しばらくベッドで寝たきり状態でした。
仕掛り中の和室には、スマート温湿度計とネットワークカメラも設定していたので、湿度が高くなりすぎていないかとか、カビが大発生してしまっていないか、ちょこちょこ覗いていました。まあカビ大発生しても、手も足もでないんですが。
退院後、施工業者にお願いして雨戸の交換をしてもらいました。元々の木製雨戸は、朽ちてボロボロになってしまっていたからです。
新しく取り付けてもらった雨戸はこれ。「え、どれ?」と思うかもしれませんが、ブラインドのように見えるのがそうです。興味ある方は「エコ雨戸」で検索してみてください。ブラインドと同じように、羽を開け閉めできる雨戸なんです。カギもかかるので、夏なら窓ガラスを開け、網戸のまま寝ることもできます。
職人さんが雨戸交換の作業をしている間、私は網戸の張替え。実は網戸を自分で張り替えるのも今回が初めてです。思っていたよりずっと簡単でした。
セルフリノベ作業を再開したのは、9月10日のこと。
手術から一か月が経過し、手足の動きはまだ思わしくなかったものの、このまま大事を取り続けていたら逆に筋肉も衰えて、復活が難しくなるだろうなと思ったので、無理せずできることから始めることにしました。
上の写真は、下地を根太(床下を支える角材)に固定する作業の後です。板の上に黒い線があると思いますが、その下に根太があります。黒い点々がビス。
この線をまっすぐ引くために使ったのが・・・
「墨壺(すみつぼ)」
と呼ばれる道具です。
墨をつけたタコ糸を板の少し上でぴんと張り、指で糸の一部を軽く持ち上げてから離すと、反動で糸が床にまっすぐ叩きつけられます。それによってまっすぐな線を引くという、日本の伝統的な大工道具です。
自分がこれを初めて知ったのは20代の頃。ゼネコンの仕事で中米のドミニカに駐在していた知人のところに遊びに行こうとしたら、「買ってきてほしいものがある」と頼まれたうちのひとつがこれでした。日本にしかないんだそうです。
7月は、車で2往復2時間くらいかけて、銚子のホームセンターまで丸のこをレンタルしに行っていたのですが、奮発してHIKOKIの丸のこを買ってしまいました。一連のセルフリノベで買ったものの中で最高額です。
これのおかげで、木材カットの時間は格段に早くなりました。術後後遺症で身体はちょっと不自由になりましたが、「失ったものを数えるな、残されたものを最大限生かせ」 「それでダメなら金で解決だ!」ということで。
荒板で作った床下地の上に、さらにレベル合わせの根太を並べ、合間に断熱材の「スタイロフォーム」をカットして敷き詰めていきます。
「レベル合わせ」ってどういうことかというと、もともと和室で畳があったので、それをフローリングにすると畳の厚みの分だけ床が低くなってしまいます。廊下とのバランスも悪くなるので、調整が必要なのです。他のやり方もあるのですが、自分は床下断熱もしたかったので、こうしました。
ちなみに「スタイロフォーム」は発泡材なので、カッターで簡単に切ることができます。
そして、厚み12mmの合板を並べていきます。これはまだ最後の床ではなく、この上にフローリング材やクッションフロアを敷いたりして完成です。ただ壁作業をする際に脚立を使って傷つけてしまう可能性もあるので、仕上げは後回しです。
ちょっと苦労したのが、出窓下や出窓脇(雨戸が入っている戸袋の裏側)の床板の処理です。この段階ではまだ、これらの空間は部屋の一部として活用する予定だったので、どうすればいいか真剣に悩んでいました。
結論としては、構造的な強度の懸念から空間活用はあきらめすべて壁裏に埋め戻してしまったので、こんなことしなくてもよかったのですが。
ここでもう一個、重要なツールを追加購入しました。ずっとメジャーと呼んでいましたが、金属製のものは「コンベックス」という名前だそうです。
これ、一番最初に買うべきものでした。
それまで使っていたコンベックスは電工用のもので、用途の違いからこのTAJIMA製のコンベックスほどの精度や機能がなかったからです。
おそらくDIYはすべてそうだと思うのですが、一番大事なことは
「正確な計測」
です。これがちゃんとできていれば、その後の作業はすべて楽だし、効率的になりスピードもアップします。そして仕上がりも美しい。実際これを使い始めてから、あらゆる作業がスピードアップしました。
いよいよ、壁です。
床には分厚いブルーシートを敷き詰めました。
まず最初にやったのが、石膏ボードを取り付けるための「間柱」の追加設置です。木造住宅の構成部材の名前はこちらのページ を参考にしてください。
家の構造の主役である「柱(通柱)」があり、その間で壁を支える垂直の木材が「間柱」。和室だった時は、柱は手前部分が露出していたのですが(真壁工法)、洋間では一般的にそれを壁裏に隠ぺいします(大壁工法)。そのため、柱と同じレベルのところに間柱を新たに立てる必要があるのです。
写真では、壁の上の方に青いものが見えていると思いますが、スタイロフォームです。天袋の裏も断熱するため、下からぎゅーぎゅー押し込みました。
そして柱・間柱の間にもスタイロフォーム。
これは作業再開して一週間ちょっとの9月19日に撮影したものです。
作業を進めながらちょっとずつ買い足して、最終的にはこのくらいの道具が揃いました。この後、石膏ボードの切り口を削るカンナや、壁紙を張るための道具とペンキを塗るための刷毛などが加りました。セルフリノベに最小限必要なものはだいたいこれで全部かなと思います。
10月1日。ほとんどの場所の間柱&断熱材が終わりました。残っているのは出窓下&出窓脇、そして押入れ内です。そこは最終的にどうするかがまだ自分の中で決めかねていて、保留になっていました。
こんなものもホームセンターのカインズでレンタルしてみました。電動サンダー。紙やすりを挟んで、木材などを磨くのに使う工具です。一泊二日で500円。
これを使って押入れの間の柱を磨くとこのとおり(上部が磨いたところ)。それまで、押入れや扉脇の柱をどう処理するか悩んでいたのですが、これを試したことで「古い柱をそのまま生かすで大丈夫」ということもわかりました。どうしても劣化が気になるところは、ペンキ塗装でなんとかなるだろうと。
握力もだんだん復活してきたので、近くのホームセンターで石膏ボードを購入してきました。これが壁になります。一年前の自分は30年以上という長いキャリアを誇るペーパードライバーでしたが、今や軽トラに資材を積んで、細い私道をバックで入ることもできるようになっています。
車の運転もセルフリノベもそうですが、「自分には絶対無理だ・・・」という心のストッパーを外すと、結構いろいろなことができちゃうものですね。それに気付くまで半世紀もかかっちゃいましたよ。
石膏ボードは、ホームセンターでは高さ1820mmのものしか買えなかったので、北側の天袋下の壁はあと少しだけ高さが足りず、水平方向に胴縁を追加しました。
そして、石膏ボードをカットして壁に固定していきました。
部屋の真ん中にある作業台は、それまで客間にあったものです。床ができたので移動することができました。
石膏ボードは、本当は厚み12.5mmのものを使うべきなのですが、それだと自分の腕ではもちあげるのが精いっぱいになってしまうので9.5mmのものにしました。カットは簡単で、カッターで切込みを入れた後、パキッとまげて折って、さらに反対側の紙を切るだけ。ノコギリも不要です。
石膏ボード作業のために買ったものがいくつか。
まずビスは「ボードビス」と呼ばれる石膏ボード専用のものです。頭部分がでこぼこしていて、後でパテを塗った時に接着しやすい作りになっています。
金属製のちょっとそろばんチックなものは、カットした石膏ボードの断面を平らにするための専用やすり。その横にあるのがカンナで、端を斜めにカットすることもできるものです。石膏ボードと石膏ボードのつなぎ目が、後で壁紙を張った時に盛り上がってしまったりしないよう、斜めに角をとった上でパテを使ってまっ平らにするのです。そのために必要な道具です。
あと実際にはほとんど使わなかったのですが、ボードビスは締め付けすぎるとめり込んで石膏ボードを割ってしまいます。それを防ぐため、わずかにめり込んだところで自動で電動ドライバーを停めるビス用ビッドも買いました。
重宝したのが、腕に巻きつける強力マグネット付きのアームバンドです。数年前「バイク整備の時に使えるかも」とコーナンで衝動買いしたものの、ほぼ一度も使っていませんでした。
ここにビスを貼り付けておくことで、次々ボードにビスを打ち込んでいくことができます。とりわけ、脚立を使って天井付近の作業をしている時には必須のツールでした。
石膏ボード作業に入ったことで、ずっと先送りしていたけどついに避けては通れない作業にも直面しました。それは
「コンセント増設」
です。
この和室にはコンセントが一か所しかなく、それも押入れの下だけでした。
そりゃそうですよね。44年前の1980年の家電製品なんて、冷蔵庫と洗濯機、あとラジカセくらいです。一か所だけのコンセントも、想定されていたのは掃除機と、夏の寝苦しい夜の扇風機くらいだったのではないでしょうか。
そのコンセントをどう増設するか。どこからケーブルを分岐させてどこにとりつけるか、決めかねていたのです。
ちなみに私は3年ほど前に第二種電気工事士の資格をとったので、自宅のコンセント増設くらいなら問題なくできます。配電盤交換などは、間違えると家を燃やしてしまう可能性もあるのでプロに頼みます。
悩んだ結果、天井裏でケーブルを分岐して、壁裏に通して新しいコンセントを作ることにしました。これは脚立で天袋に上って腰掛けて下を見下ろした図です。
天井裏はこんな感じでした。
おそらく太い角材の上は這って歩いても大丈夫だとは思うのですが、うっかり天井板を踏み抜いて下に落ちると命にもかかわるので、やめました。
そのかわり、紐の先に重石になるものをつけ、投げて壁裏の隙間の近くに放り込む。それを壁と天井の隙間から手を差し込んで引っ張り、その紐を使って電気のケーブルをそこまで運ぶという戦略に。
きっと難しいよなあ・・・でもこれをやらなかったら、次のステップにいけないから何時間かかってもめげずに頑張ろうと思ったのに、まさかの2回目の投てきで成功。我ながらびっくりしました。
うれしすぎて、ドヤ顔ですw
コンセントは、石膏ボードをくりぬいてそこからだし、上にプラスチックの枠をはめます。壁紙を張る時にはまたこのプラスチック枠を外して、壁紙の上から止め直し、カバーをつけたら完成です。
石膏ボード張りも完了。力がでない身体での作業だったので、結構きつかった記憶です。下の段はまだいいのですが、上は脚立に乗った状態で持ち上げて固定しないといけなくて、出窓や扉の上は「試練」といってもいいほど。安全のため、本来なら大きなまま張れる場所も、二分割して持ち上げたりしました。
あとさんざん悩んだ出窓下と出窓脇も、結局壁裏に封じ込めちゃうことに。というのも、構造を支える柱より外側に外壁があり、そこは実は宙に浮いた状態になっているんです。その空間を部屋として使おうと思うと、内壁側にも耐火を兼ねた石膏ボードを貼り付けないといけないですし、そうやって加わる新たな重量に外壁が耐えられるのかどうか、素人には判断ができません。
一応、雨戸施工の職人さんのアドバイスをもらって、7月の段階で・・・
外壁の下にこんなサポートを追加したんですが、素人のやったことでブロックも地面に軽く埋めただけ。大きな地震が来たら簡単に外れちゃうと思います。
なのでリスクは回避することにしました。
そして11月、遂に仕上げの「壁紙貼り」に入るのですが、ちょっと記事が長くなってしまったので次回にします。
>続く

































 X(旧Twitter)アカウントはこちら
X(旧Twitter)アカウントはこちら